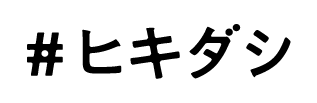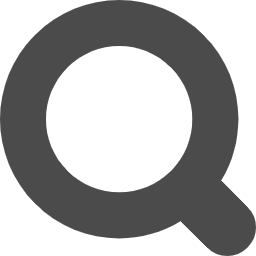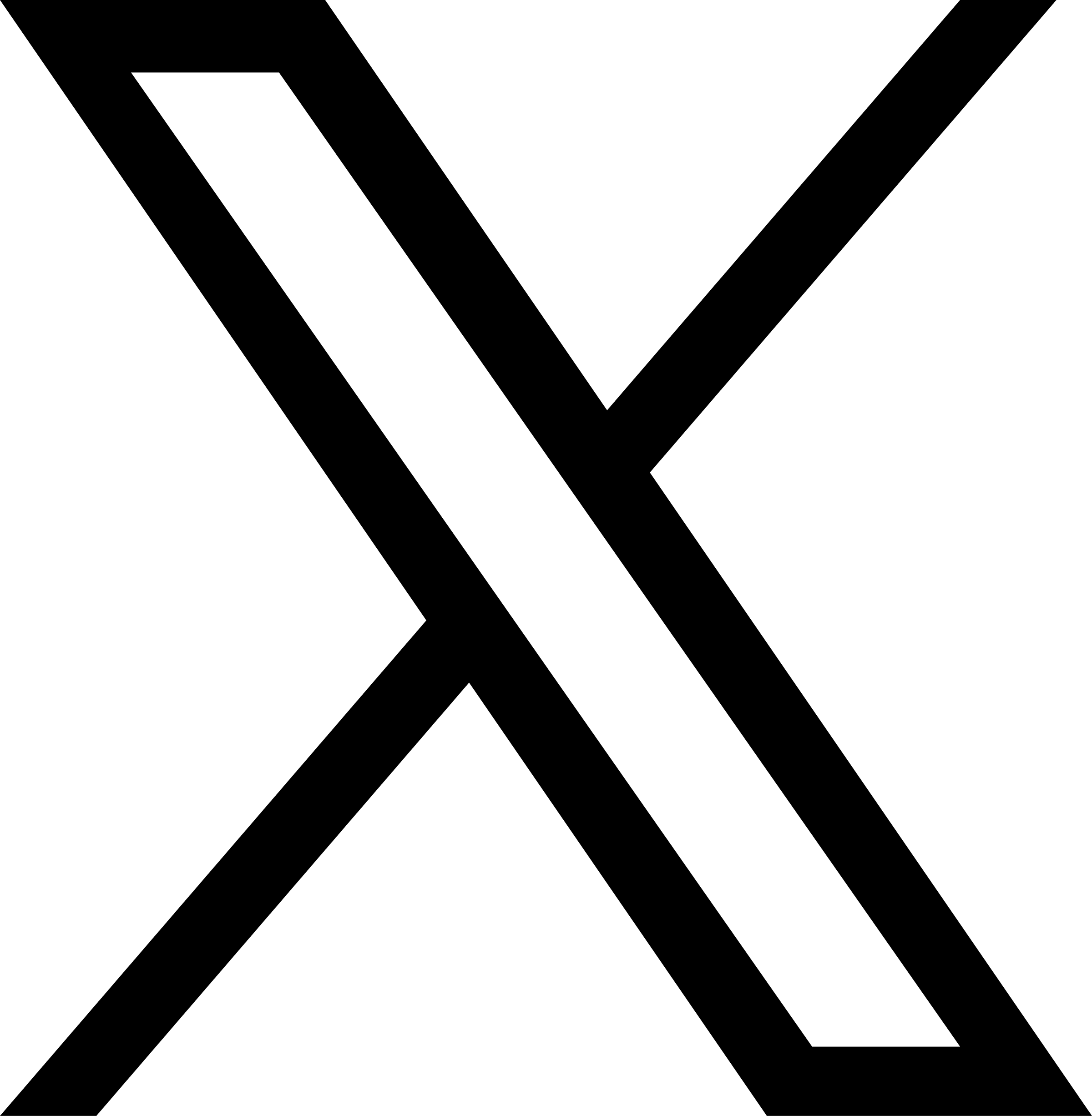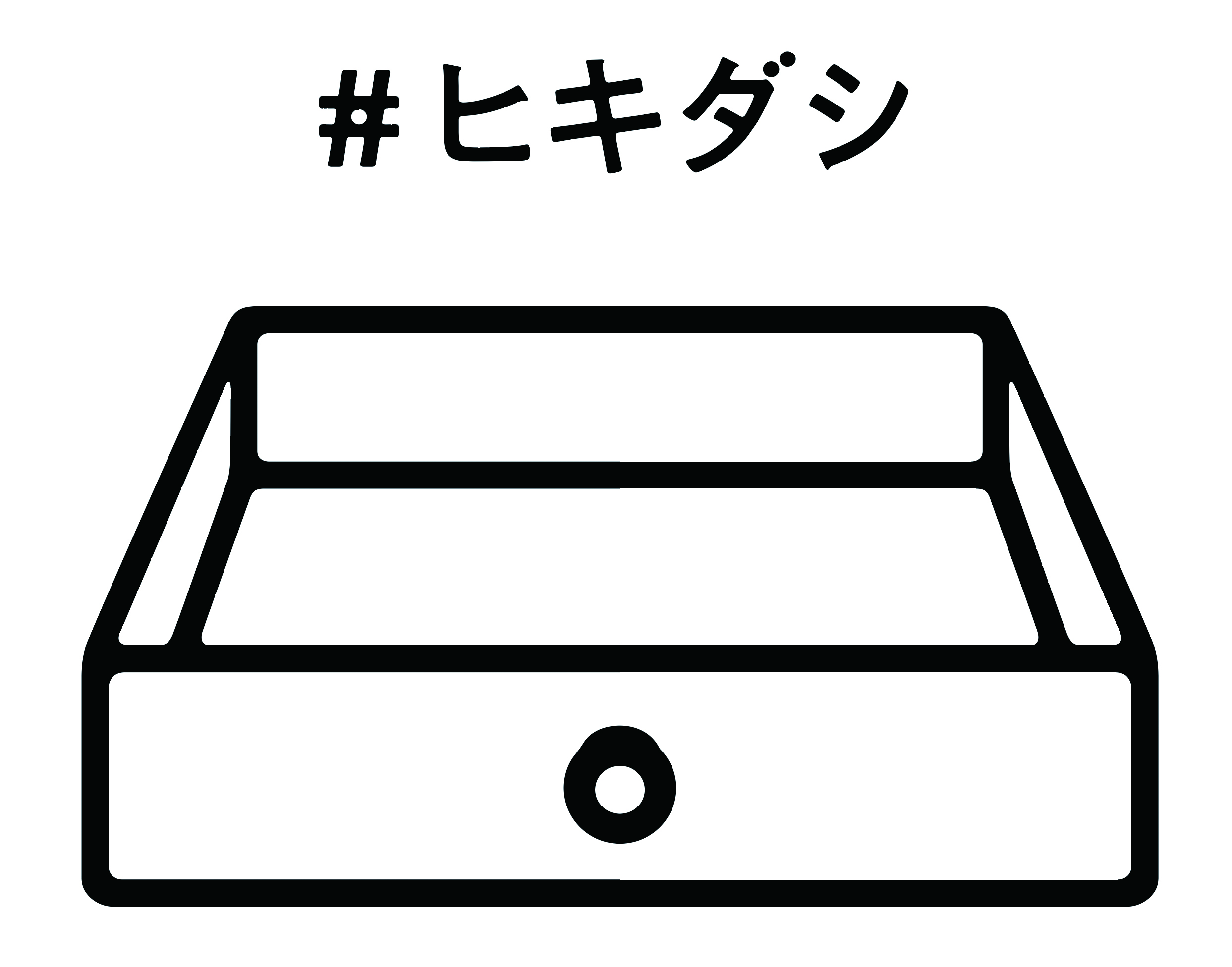お金の#ヒキダシ

子どもが1歳です。毎月どれくらい子どものために貯蓄したらいいかわかりません。また、他にどういう手段がありますか。
中予地区
子どもの将来を憂い、備えるための貯蓄、大変よく分かります。が、幼少期には貯蓄よりも投資することの方が「教育経済学」の観点からも有効です。貯蓄は小学校入学以降から考えたのでもいいかもしれません。ご家族の議論の一助になれば。
「4歳のときの100円が60年後には300倍に」
https://www.recruit-ms.co.jp/issue/interview/0000000528/
はじめまして、早速ですが、ご相談の件ですが、まずは、ご家族の素晴らしい人生を、伴走いただけるファイナンシャルプランナーの方と一緒に、ライフプランニングの実施、体験をオススメ致します。
ご相談いただき、ありがとうございます。
お子さんが1歳という大切な時期に、教育費について考え始められたのは本当に素晴らしいことです。将来のための準備をするのは、決して簡単なことではありませんが、一歩一歩進めることで、きっと理想の形に近づけます。
無理のない金額から始めて、少しずつ貯蓄のペースをつくることで、安心感が得られると思います。今回お伝えした内容をもとに、貯蓄や資産運用の方法を検討していただき、お子さんの未来を支える計画を進めていきましょう。
お子さんの将来が、笑顔と希望に満ちたものでありますように★
❶子どものための貯蓄、毎月どれくらい必要?
教育費の必要額は、進学パターンによって異なります。まずは、お子さんの進学プランを想定し、大まかな金額を見積もりましょう。
【進学パターン】 【総額】 【月額の目安(18年間)】
幼稚園~大学まですべて公立 約1,000万円 約4.6万円
幼稚園~高校が公立+大学私立文系 約1,600万円 約7.4万円
幼稚園~大学まですべて私立 約2,600万円 約12万円
進学パターンが未定の場合、まずは大学入学時点で「400万円」を目標にすると良いでしょう。これは、国公立大学や私立文系の初年度費用と2年間の在学費用に相当します。
計算例: 400万円 ÷ 18年間 ÷ 12ヶ月 ≈ 毎月約1.9万円
「最低限これくらい」という金額を目安に、余裕がある場合は少しずつ上乗せしていくことで、将来の選択肢を広げられます。
❷貯蓄以外の教育資金準備の方法
教育費の準備には、貯蓄以外にも以下の手段を組み合わせることで、効率的にリスクを分散できます。
A:学資保険
メリット:教育資金を計画的に貯められる。万が一、契約者(親)が死亡しても保険料の支払いが免除され、満期金が受け取れる。生命保険料控除の対象になる。
注意点:現在の低金利の影響で、返戻率が100%未満になる場合がある。中途解約すると元本割れのリスクがある。
おすすめプラン:返戻率が高い商品を選び、大学進学時の資金準備を目的に活用する。毎月の保険料を無理のない範囲で設定(例:毎月5,000円~1万円)。
B:積立預金・定期預金
メリット:元本保証があり、リスクが少ない。自動引き落とし設定で着実に貯められる。
注意点:金利が低いため、大きなリターンは期待できない。
おすすめプラン:確実に貯めたい部分を毎月積立(例:毎月1万円)。児童手当を専用口座で貯蓄することで、教育資金を着実に確保。
C:NISA(少額投資非課税制度)
メリット:運用益が非課税(通常は20.315%課税)。長期運用で資産を増やす可能性がある。
注意点:元本保証がなく、経済状況によっては元本割れするリスクがある。投資対象の選定が難しい場合がある。
おすすめプラン:教育費全額をNISAに頼らず、一部を分散投資(例:児童手当の一部をNISAで運用)。投資初心者はリスクを抑えた商品を選ぶ。
D:児童手当の活用
児童手当を全額貯金に回すことで、約200万円を準備できます。
【児童手当(月額)】 【受取期間】 【合計額】
15,000円(3歳未満) 36ヶ月 54万円
10,000円(3歳~中学生) 144ヶ月 144万円
活用法: 児童手当を貯金専用口座に入れることで、自然に教育資金を貯める。
❸贈与税に関する注意点
教育費は通常贈与税がかからない: 必要な都度支払う場合や、「教育資金一括贈与非課税制度」(最大1,500万円非課税)を活用可能。
名義預金の注意点: 子ども名義で親が管理している口座は、贈与税の課税対象となるリスクがある。
対策:必要に応じて親の名義で管理し、都度支出する。祖父母からの支援には非課税制度を利用。