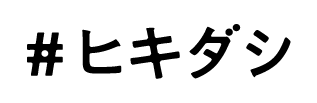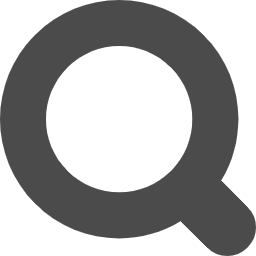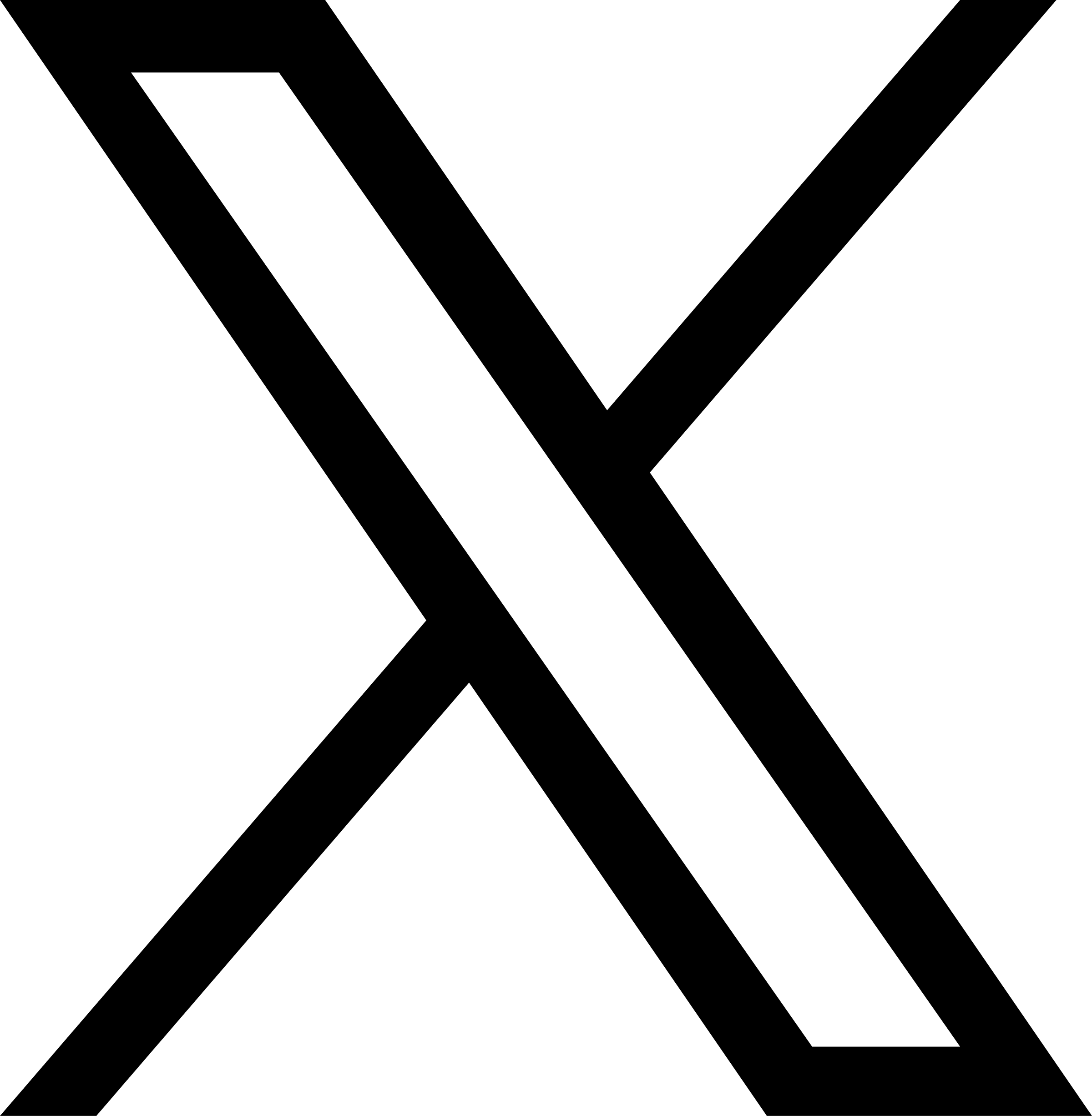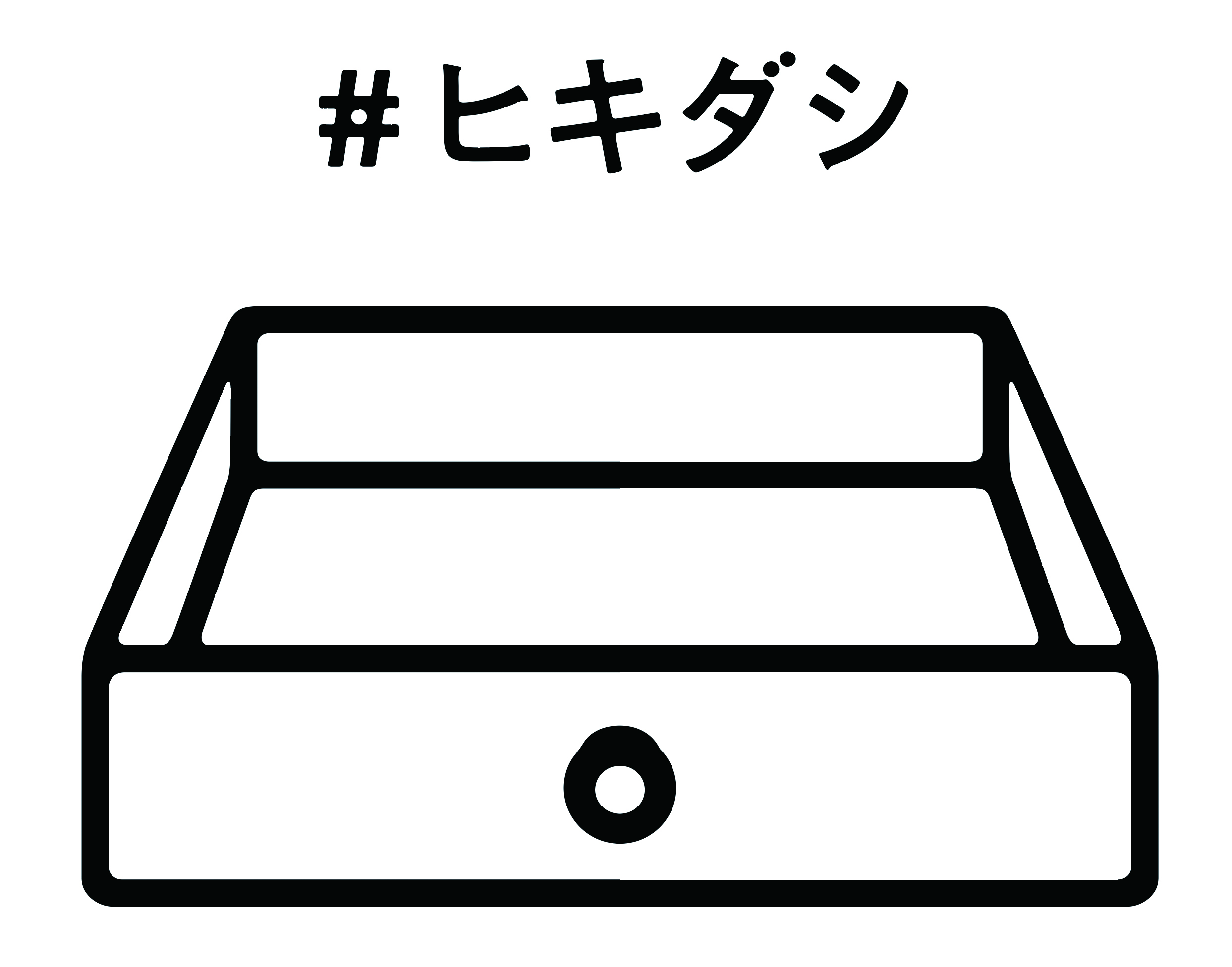からだの#ヒキダシ

今では「熱中症」という言葉が定着していますが、私が子供の頃(40年ほど前)は「日射病」と言っていました。いつ頃から呼び名が変わっていったのでしょうか。
中予地区
ご相談いただき、ありがとうございます。
「昔は『日射病』って言ってたのに、最近は『熱中症』ばかり。いつの間に変わったのかしら?」という疑問、同じように感じていらっしゃる方、実はとても多いです!
まず、「日射病」というのは、強い日差し、つまり直射日光を長時間浴びたときに起きる体調不良のことを指します。炎天下で帽子もかぶらずに遊んでいたあの頃、「頭がクラクラして、気分が悪くなった」という経験がある方も多いのではないでしょうか。
一方、「熱中症」という言葉は、屋外・屋内を問わず、暑さによって体の中に熱がこもることで起こる症状全体を指す、より幅広い意味の言葉です。たとえば、風通しの悪い部屋でクーラーも使わずにいるときや、夜間でも熱中症になることがあります。
つまり、「日射病」は「熱中症」の一部にあたります。
ご指摘のとおり、40年ほど前(1980年代ごろ)までは、「日射病」や「熱射病(ねっしゃびょう)」といった言い方がよく使われていました。まだ今のように熱中症への理解が深まっていなかった時代です。
ところが、1990年代後半から2000年代にかけて、夏の気温が年々上がり、室内でも倒れる人が出るようになったこと、また高齢化が進んだことなどから、医学的にも「熱中症」という言葉が注目され始めました。
ちょうどその頃から、環境省や厚生労働省が「熱中症予防」の啓発活動を本格化させ、テレビや新聞、そして学校教育などでも「熱中症」という言葉が一気に広まりました。今では保健室の掲示や救急講習でも、完全にこの言葉が定着していますね。
「昔は水を飲むなって言われてたのよ」なんて思い出もありますよね。昭和の部活動や運動会では、水を飲むとバテるとか、お腹が痛くなるなんて言われていた時代がありました。
でも今は違います。「のどが渇く前に、こまめに水分と塩分をとる」ことが熱中症予防の基本になっています。特に50代以降は、暑さに対する感覚が鈍くなることもあるので、早め早めの対策が大切です。
「日射病」から「熱中症」へ。言葉の変化は、医学の進歩と、私たちの暮らしの変化を映し出しています。昔の呼び方に懐かしさを感じつつも、今の知識でしっかり自分の体を守っていきたいですね。
どうか今年の夏も、無理をせず、エアコンや水分補給を上手に活用して、元気にお過ごしください!!