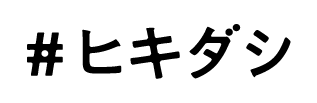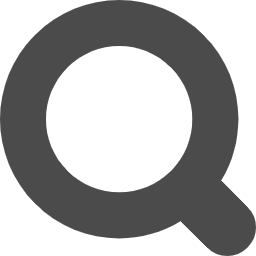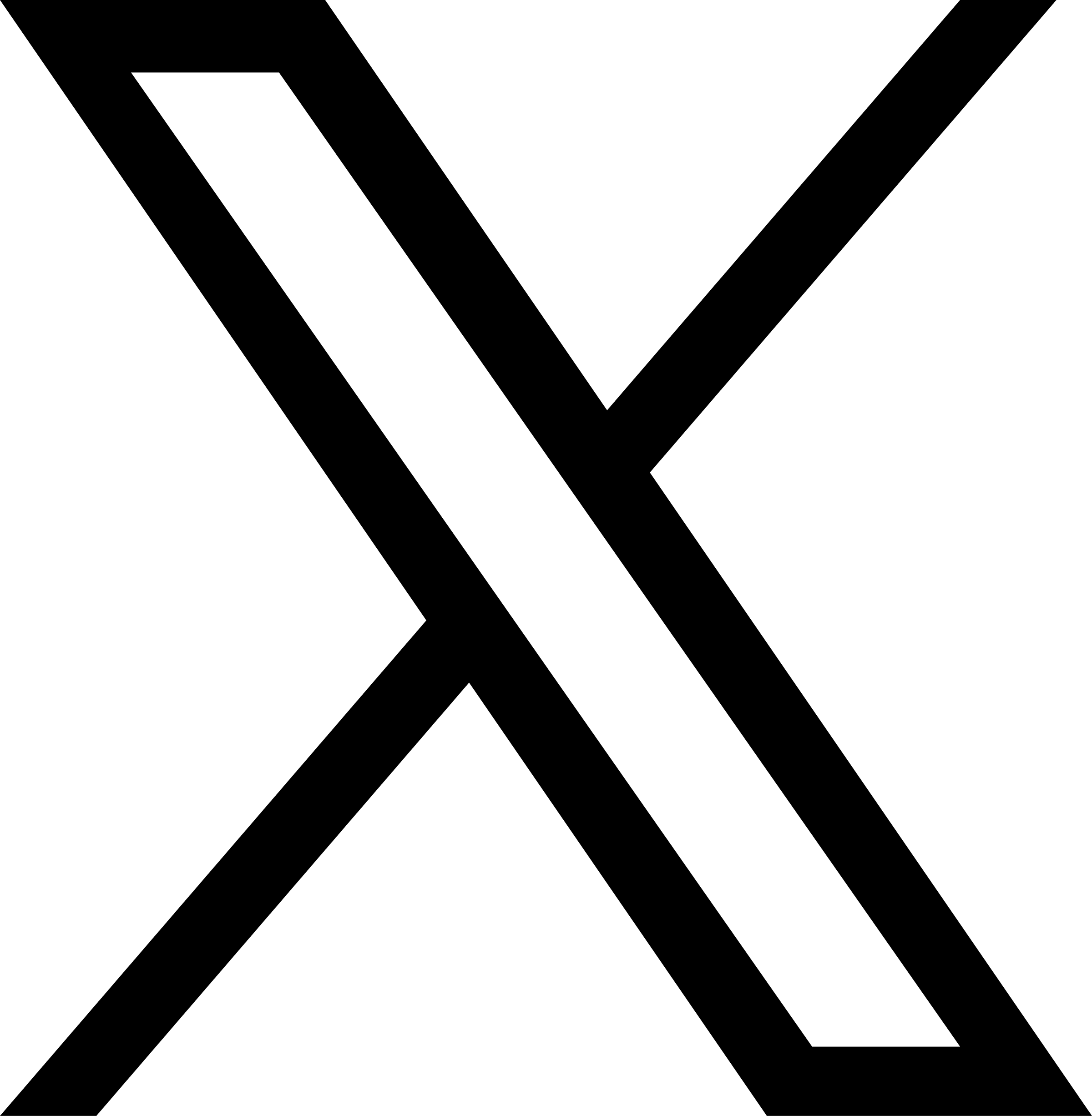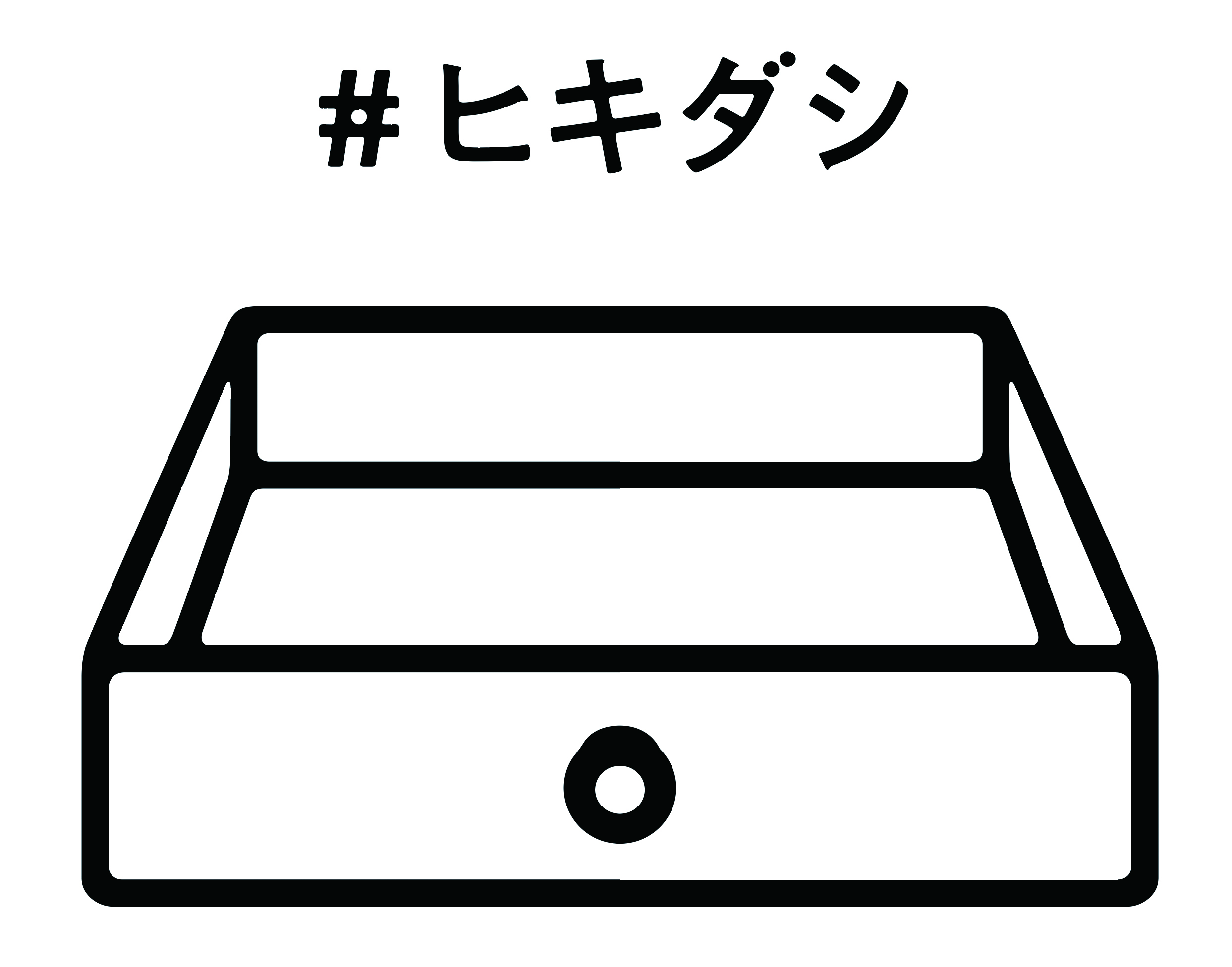学びの#ヒキダシ

七夕の由来を教えてください。
中予地区
今日は7月7日ですね!素敵なご相談をありがとうございます。
一年に一度だけ、織姫と彦星が天の川を渡って会えるという、ロマンチックな物語が有名ですよね。実は、七夕はもっと奥深くて、長い歴史と文化がぎゅっと詰まった日なんです。
七夕の原点は、中国の古い年中行事「乞巧奠(きこうでん)」にあると言われています。
7月7日の夜、女性たちは織姫星に手芸や裁縫が上達しますようにと願って、お供えをして祈っていたんですね。針に糸を通したり、果物や酒を並べたりして、空を見上げていたそうです。
いわば、「がんばる自分を後押ししてくれる星」に願う日だったんです。それって今の私たちが「努力が報われますように」と願う気持ちと、とても似ていると思いませんか。
この乞巧奠が日本に伝わったのは、奈良時代(いまから約1300年前)。ちょうどその頃、日本にも「棚機(たなばたつめ)」という行事がありました
これは、清らかな乙女が機(はた)を織りながら神さまに豊作や無病息災を祈る、神聖な儀式。場所は川辺の機屋(はたや)、まるで水音とともに神に祈りをささげる、幻想的な光景が思い浮かびます。
中国の「技を願う星まつり」と、日本の「神に祈る機織りの儀式」。このふたつが融合し、今の七夕という行事が生まれたようです。
「たなばた」は本来「棚機(たなばた)」という日本語の読み方で、のちに「七夕」という漢字があてられ、日本と中国、それぞれの文化が優しく溶け合ってできた行事です。
今では当たり前の「短冊に願いを書く」という習慣。これも、はじまりは「手芸や勉強の上達を願う」ことでした。江戸時代になると、寺子屋(いまでいう塾)の子どもたちが、「字が上手になりますように」「勉強ができるようになりますように」と、色とりどりの紙に願いを書いて笹に吊るしました。
「誰かに幸せにしてもらいたい」という願いじゃなく、「自分が努力したい」「少しでも成長したい」という前向きな願いだったこと。
笹竹はまっすぐ天に伸びる植物。「自分の願いが空まで届きますように」と、そんな気持ちも込められていたんです。
ちなみに、短冊の五色(青・赤・黄・白・黒)には、自然のバランスを表す「五行思想(ごぎょうしそう)」という中国哲学が隠れていて、自然と調和しながら願いを叶えるという意味もあります。